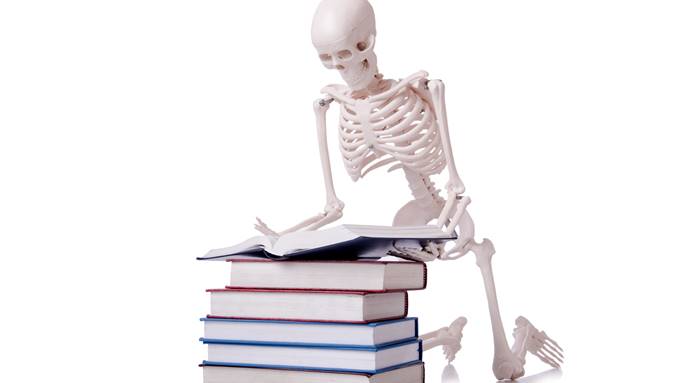ゆういち
ゆういち理学療法士生活約20年。たくさんの1年目理学療法士を見てきたゆういちです。
大学が専門学校を卒業し、国家試験に合格していよいよ理学療法士になっても、一人前として働くのは難しい。
学校で学ぶ知識や技術など、臨床で必要なことの100分の1あるかどうか、そんなちっぽけなものです。
1年目はとにかく勉強しないといけない。
そんな当たり前のことはわかっていても、どんな方法で勉強するのがいいか、わからない人は非常に多いです。
先輩理学療法士について治療を学ぶのかいいのか、それとも講習会に行くのがいいのか、はたまた文献を読むべきなのか。
 妻ちか
妻ちか楽して成長する方法はないんやろうけどね。
 ゆういち
ゆういちでも、できれば一番近道で成長できる方がいいに決まってる。
そこで今回は、100人近い新卒理学療法士を見てきた私が、一番成長できると思う方法をご紹介します。
正しく勉強できれば、2年目、3年目のあなたに大きな結果をもたらします。
よくある勉強方法のメリットとデメリットもご紹介しますので、いまの方法と照らし合わせてくださいね。
理学療法士1年目は何でも吸収してしまう
理学療法士1年目の特徴はずばり吸収力。
日々の業務に追われて、不安や悩みを抱えながらも、毎日が新しい発見の連続で、働くことが楽しい時期です。
見るもの触れるものなんでも興味がわいて、自分に必要な知識や技術と思い込んでどんどん吸収していきます。
 妻ちか
妻ちか私も1年目は楽しかったなぁ。
 ゆういち
ゆういちそうやなぁ。もう20年くらい前かぁ・・・。なつかしい。
逆に吸収しすぎて、何が患者さんにとって必要なことなのか、わからなくなってしまうことも。
そうならないように、管理職や上司が講習会を制限したりすることもあるようです。
ですから、1年目の勉強では自分に必要なものをひたすら吸収するのが、成長への近道といえるでしょう。
患者さんや自分の将来のために必要な治療技術や知識は何か、そしてそれを獲得するにはどうすればいいか、しっかり理解する。
新人理学療法士勉強には経験と考察が重要
今回の記事の結論になりますが、新人理学療法士の勉強では、
- 患者さんや利用者さんに触れるという経験をする
- 考察を繰り返す
これしかありません。
 妻ちか
妻ちかやっぱり患者さんからしか学ばれへんってこと?
 ゆういち
ゆういちそう。ただ、その後に「考える」ってことも大事。
たとえば、人工肩関節置換術を施行された患者さんを担当したとしましょう。
学生時代に人工肩関節の患者さんを担当することはないでしょうから、最初は戸惑います。まずは自分ができる評価や治療をして、それでもおそらくうまくいきません。
「何かが足りない」と、新人なら誰でも考えます。
大切なのはここからです。
理学療法士でも作業療法士でも、先輩セラピストに教えてもらうのは簡単。それなりの答えはもらえるでしょう。
でもね、自分で考えないと成長は望めませんし、仕事のやりがいを感じることはできません。
治療がうまくいかなければ、教科書や文献を調べて知識を補充するでしょ?それでも足りなければ、勉強会に参加して技術を習得しようとします。
なぜその症状になっているのか、よりよい治療はないか、疑問を持ち続ければ自ずとやるべきことが見えてきます。
自己満足せずに、課題と真摯に向き合う。もがき苦しんむ経験が必要です。
そうして自分の課題を少し解消していくことで、壁を乗り越えることができます。
どうしても課題が解決しないときに、必要最低限を上司や先輩が助けてもらえばいいのです。
 妻ちか
妻ちか自分で考えて必要なことを勉強するってことやね?
 ゆういち
ゆういちうん。職場や先輩から課題を与えられるだけじゃ、受け身の人になってしまう。
 妻ちか
妻ちかそう考えると、症例発表を義務みたいにやらされるのはあかんなぁ。
 ゆういち
ゆういち症例報告は義務じゃない。聞いてもらってアドバイスが欲しいからやるんよ。
1年目ならみんな一生懸命だと思いますが、どのように日々精進しているかは本当に大事なので、これは間違えないでください。
1年目から自分で考えて、課題と向き合って努力できる人は2年目、3年目に大きく飛躍する。そしてこれは理学療法士の大切な資質でもある。
新卒理学療法士の勉強法のメリット・デメリット
新卒理学療法士が苦手分野の克服のためにやる勉強法には、メリットとデメリットがあります。
よくある勉強法についてご紹介しますので、いまの自分の勉強法のメリットとデメリットをぜひ知ってください。
理学療法士の参考書や教科書は最低限の知識と考えよ
新人の勉強で真っ先に思い浮かぶのは、理学療法の参考書や教科書を読むことです。
 ゆういち
ゆういち自分たちが新人の頃は本の種類が少なかったけど、最近は増えたよなぁ。
 妻ちか
妻ちかそれだけ理学療法士だけじゃなく、作業療法士も言語聴覚士も増えたってことかな。
参考書や教科書で勉強することのメリットとデメリットは次の通りです。
- 学校で学んだことの延長上にある、基礎的な内容は一通り学べる。
- 本の種類が多いので、症例に必要な情報を得るために使える。
- 職場でも自宅でも気軽に勉強できる。
- 専門知識や治療技術については学べないと考えた方が無難。
- 値段が高いので、たくさん本を買えない。
- エビデンスがあるかどうか、あやしい本も多い。
基礎を学ぶには参考書や教科書がいい。あと初心に戻りたいときにも、参考書や教科書に戻るものあり。いきなり難しい本を読む必要はありません。
理学療法士1年目から勉強で文献を読む習慣を作ろう
参考書や教科書と比較されるのが文献です。
よく目にする文献では理学療法、理学療法士ジャーナル、総合リハビリテーションなどがあります。
文献を読んで勉強することのメリットとデメリットは次の通りです。
- 参考書や教科書よりも実践的な内容が書かれている。
- 特集号なら、その疾患の知識を相当深められる。
- 勤務先の病院や施設が定期購読していれば毎月文献が届くので、参考書や教科書より触れる機会が多い。
- 特集にもよるが、当たり外れがある。
- 自分が求めている疾患や治療がずばり解説されることは稀。
- 勤務先が定期購読していなければ、購入して読まないといけないのでお金がかかる。
一歩突っ込んだ知識を身につけるなら、文献は読むべきですが、文献に触れる機会はすぐ手に入るような環境があるかどうかに左右されます。
大学病院とか、大きな総合病院だと文献がダウンロードできる環境にあるので触れやすいです。そんな方は理学療法だけでなく、医師の雑誌や英語の文献も積極的に読んでください。
病院独自の研修プログラムは新人教育に病院の色がでる
最近増えているのが病院独自の研修プログラムです。新人育成を目的に実施されています。
こちらは病院で行われる新人研修プログラムの一例です。
- 4月:法人内研修(就業規則、接遇、身だしなみ、マナー、コミュニケーションスキル、電話対応、他部門見学など)
- 4~5月:リハ科内研修(医療保険・介護保険制度、リスク管理、書類作成)
- 5月~:疾患についての研修
- 10月以降:症例発表、レポート提出、研究開始
法人の研修(病院や施設全体のところもあり)では、社会人や医療従事者としての心構えを学びます。
一方、リハビリテーション科内の研修では理学療法士として現場で必要な基礎を学び、その後専門知識や技術を学んでいきます。
触診や動作観察、動作分析などの評価や、病院によってはテクニックを学べる場合もあります。
病院や施設内独自の研修プログラムのメリットとデメリットは次の通りです。
- 社会人や医療人としてのマナーや常識を教えてもらえる。
- しっかりスケジュールが組まれて、目標が予め設定されているのでそこを目指せばいいだけ。(あれこれ考える必要がない)
- 段階を踏んで疾患のこと、患者さんのこと、治療技術を学べる。
- 法人が大きければ、他部門、他分野のことも学べる。(急性期・回復期・生活期など幅広い病期や、老健・訪問リハビリテーションなど)
- 内容がいまいちな研修プログラムを組んでいる法人も多い。
- 内容に偏り(◯◯法や△△手技を押し付けられる)
- 法人が小さいと他部門や他分野はそれほど多く学べない可能性もある。
文献を読んだり、講習会に参加するのとは違い、これは入職して勤務していれば必須になる。
これだけ幅広く、時間をかけて仕事について教えてもらえる機会は今後ないから、そういう意味では有意義だと思う。
接遇やマナーは今後勉強できる機会はないので、しっかり身につけておこう。
プリセプター制度やOJTは担当する理学療法士で1年目の未来が大きく変わる
最近流行りなのがプリセプター制度。
プリセプター制度(プリセプターシップ)とは、厚生労働省の「新人看護職員研修ガイドライン」には次のように書かれています。
※看護師を理学療法士に頭の中で置き換えて読んでみましょう。
新人看護職員1人に対して決められた経験のある先輩看護職員(プリセプター)がマンツーマン(同じ勤務を一緒に行う)で、ある一定期間新人研修を担当する方法。この方法の理念は、新人のペースに合わせて(self-paced)、新人自らが主体に学習する(self-directed)よう、プリセプターが関わることである。
ここでのポイントはふたつ。
- 新人理学療法士(プリセプティ)1人に対して、先輩理学療法士(プリセプター)のマンツーマン体制。
- 新人のペースに合わせて、新人自ら主体的に学習するようプリセプターが関わる。
昔のセラピストの初期研修では、複数人の先輩がああだこうだと指導することが多かったです。
 ゆういち
ゆういちこれだといろんな意見が聞ける反面、意見が統一されないと新人がパニックになる。
 妻ちか
妻ちか「船頭多くして山に登る」やな。
「船頭多くして船山に登る」
指図する人が多くて方針の統一がはかれず、物事がとんでもない方向にそれてしまうことのたとえ。
引用)故事ことわざ辞典
社会人1年目では報連相(報告・連絡・相談)が大事だといわれます。
最初は右も左もわからない状態で不安ばかりなので、何かあれば先輩に確認するのは当然です。
その窓口が統一されるという意味では、プリセプター制度には大きなメリットがあります。
 妻ちか
妻ちかこう見るとメリットも大きそうやけど、プリセプター次第かな?
 ゆういち
ゆういちプリセプターは3~5年目くらいの子やから、自分の引き出しも少ないのは問題。
新人の習熟度の判断もプリセプター。
そのプリセプターの能力が新人の成長を左右します。
またプリセプターの相談に乗るのは管理職や上司ですが、その人たちが口を出すと結局船頭が多い状態になってしまいます。
 妻ちか
妻ちか最近OJTってやつもない?
 ゆういち
ゆういちあるある。OJTも増えたよなぁ。
新人向けの研修プログラムや、プリセプター制度のひとつの形といってもいいかもしれません。
最近OJT制度を導入している病院や施設も増えてきました。
OJTとは、On the Job Trainingの略で、働きながら技術や知識を習得してもらうという職業指導方法の一つです。
第一次世界大戦に人手不足の造船所で、新人工員を急きょ教育する必要に迫られた、現場監督のチャールズ・R・アレンが、教育学者ヘルバルトの5段階教授法(予備、提示、皮下k、総括、応用)を基に考察した4段階職業指導法(やってみせる→説明する→やらせてみる→補修指導)に由来するとされています。
ざっくりいうと経験重視の指導法。やっぱり臨床経験からしか学べないってこと。
これは最初に話したおすすめの勉強法に近く、OJTを採用する企業は多い。
重視する教育訓練については、正社員・正社員以外ともに、「OJT」を重視する又はそれに近い企業割合が7割を超えている。
プリセプター制度、OJTのメリットとデメリットは次の通りです。
- マンツーマン指導なので、指導方針がぶれない。
- 何か相談するときに誰に聞くべきか悩まずにすむ。
- 新入職員だけでなく、プリセプターも刺激を受けて一緒に成長できる。
- OJTでは先輩のマネをすればいいので、あれこれ頭で考えなくていいので治療現場に入りやすい。
- 自分独自のことをするより、先輩のマネをすればいいので、どこが違うのかフィードバックをもらいやすい。
- プリセプターの視野が狭いと、新人が育たない。
- 通常業務に新人指導が加わると、プリセプターの負担が大きい。
- プリセプター不在時の対応に困る。
- OJTでは自分でがんばらない人は成長しない。
- OJT教育担当となる先輩の能力次第で、成長できない可能性もある。
- プリセプター制度でもOJTでも、教育担当となる先輩と人間関係がうまくいかないと、成長どころか仕事が嫌になってしまうこともある。
 妻ちか
妻ちかプリセプター制度とOJTは先輩次第か。
 ゆういち
ゆういち先輩とうまくいかないと仕事が嫌になる。
人間関係は1年目の理学療法士にとって、一番の悩みかもしれません。
そのあたりはこちらで詳しく書いています。
人間関係が崩れると新人で辞める人もいる。先輩の責任も重い。
プリセプター制度やOJTにはメリットだけでなく、デメリットにも目を向けるべき。
OJTは真似から始めるので新人にとっては始めやすいが、なぜその評価が必要なのか、なぜその治療をするのか、考える習慣がつかず自立できない可能性もある。
プリセプター制度もOJTも先輩との信頼関係は大事なので、しっかりディスカッションすることが重要。
学会では新しい知識を得て刺激を受けろ!
理学療法士なったら、新人からどんどん学会には行くべきです。学会は最先端の知識に触れる機会でもあります。
学会で学ぶことのメリットとデメリットは次の通りです。
- 最先端の知識や、他者の取り組みを学べる絶好の機会。
- 同業者に会うことで刺激をもらうことができる
- 学会に行くにはお金がかかる。(参加費、交通費、宿泊費など)
- 休みをつぶして行く必要がある。講習会と違い手技や技術は学べない。大学や研究機関での研究の話が多いので、職場で生かせるかは微妙。
 妻ちか
妻ちか時代の流れもあるし、学会に行くと変化も感じやすいよね。
 ゆういち
ゆういち別の病院の理学療法士に会って話すと刺激にもなるしな。
講習会はエビデンス無視のものが多いので注意が必要
20年ほど前は協会主催の講習会しかなく、応募しても全然当たりませんでした。
でも最近セラピスト向けの講習会がめちゃくちゃ増えました。
理学療法士が急増し、協会主催の講習会だけでは治療技術を高めたいセラピストの欲求を満たせなくなり、次々とセミナー団体が発足します。
 妻ちか
妻ちか協会主催のとは違って、魅力ありそうな感じ出してるもんなぁ。
 ゆういち
ゆういちたしかにそういう雰囲気はある。でもそこが危ういねん。
協会主催以外の講習会は、いわば民間業者が勝手に開催している勉強会です。
名のある有名な先生を招いて有意義なセミナーを開催していることもあれば、中には低レベルで金儲け主義のセミナーもあります。
行っても意味がないセミナーも増えたので、注意が必要。
講習会で学ぶことのメリットとデメリットは次の通りです。
- 治療技術、手技を学べる。
- 講習会にはお金がかかる。特に最近は高額なセミナーが増えた。
- あやしい手技が多い。
- 宗教のような団体もある。
- 講習会独自の認定コースは、理学療法士として働く上ではあまりプラスならない。
- 金儲け主義のセミナー団体が増えた。
- セミナーのレベルが低い。
 妻ちか
妻ちかえらいデメリットが多いなぁ。
 ゆういち
ゆういち治療手技を学べることはメリットかもしれんけど、やっぱりデメリットが多いわ。
特定の手技や概念を学ぶことが悪いとは思いません。実際、私もSJF、ボバース、AKAなどの手技や概念を一通り学びました。
ただ、手技や概念が全てではないことははっきり申し上げておきます。
また「絶対治せる!」「必ずよくできる」などと誇大広告をしている講習会に行くのは大反対です。
高額セミナーには特に注意。本当にそれが必要か、見分ける目が必要
1年目の勉強なら基礎的な講習会(触診、解剖学、運動学)がおすすめ。
日本理学療法士協会の新人教育プログラムは役に立たない
書こうかどうか迷ったんですけど、理学療法士が新人教育っていわれてピンとくるのはこれかなと思って載せることにしました。
単刀直入にいうと、日本理学療法士協会の新人教育プログラムでは成長できません。
 妻ちか
妻ちかはっきりいうなぁ~ww
 ゆういち
ゆういち協会のえらい人たち、すみません。でもこれがみんなの声です。
日本理学療法士協会の新人教育プログラムとは、協会が定めたテーマに沿って研修会を受講して単位を取得します。
以前は都道府県士会が実施する研修会に参加することで単位がもらえましたが、現在はe-ラーニングでも単位がもらえます。
一部では金のかかるスタンプラリーと揶揄されています。
協会の新人教育プログラムのメリットとデメリットは次の通りです。
- 理学療法の倫理や関係法規など、普通の仕事では学べないことを学べる。
- 神経系疾患、内部障害、運動器疾患、地域リハビリテーションなど、テーマが多岐にわたる。
- 専門理学療法士、認定理学療法士になるには修了が必須。
- 基本座学なので、手技・実技は学べない。
- どこまで臨床で役立つのか疑問。
- e-ラーニングで学ぶとけっこうお金がかかる。
日本理学療法士協会の新人教育プログラムは、専門領域に進みたい人のための義務教育のようなもの。成長は期待しない方がいいでしょう。
まとめ
理学療法士1年目の勉強方法についてお伝えしてきました。
長くなったので最後にまとめます。
- 理学療法士1年目は経験と考察がとにかく大事。
- 病院独自の教育研修、プリセプター制度、OJTにはメリット・デメリットがある。
- 講習会にはあやしいものが多いので、それが本当に臨床で生かせるのか見極める目が大事。
「自分はどんなことを学ぶべきなのか?」
それをしっかり見定めて、勉強していくようにしましょう。